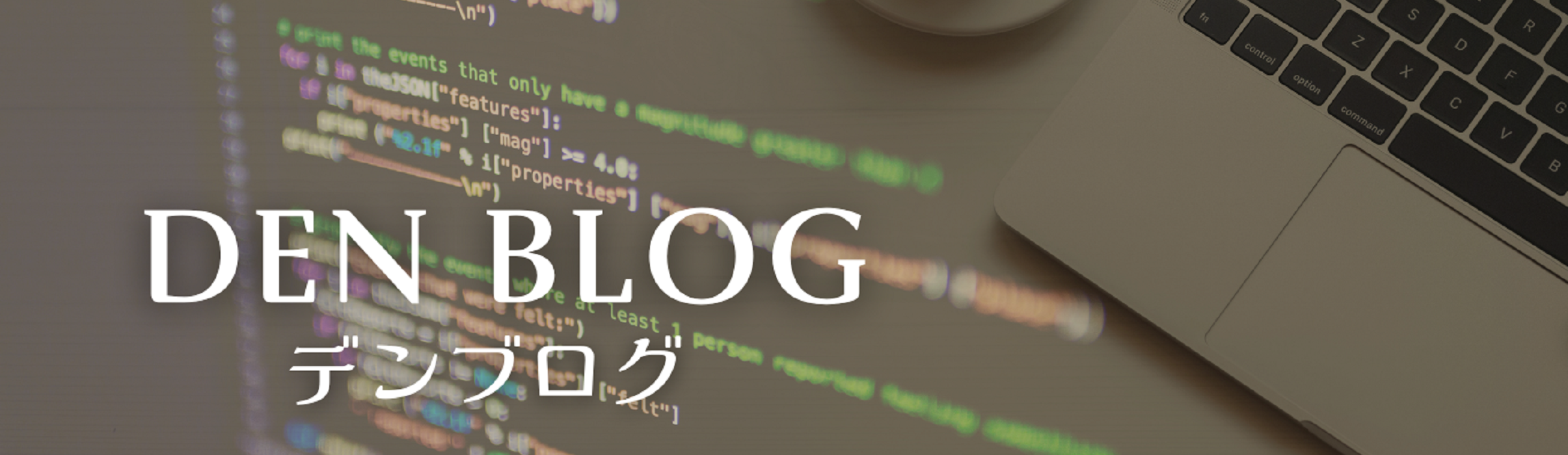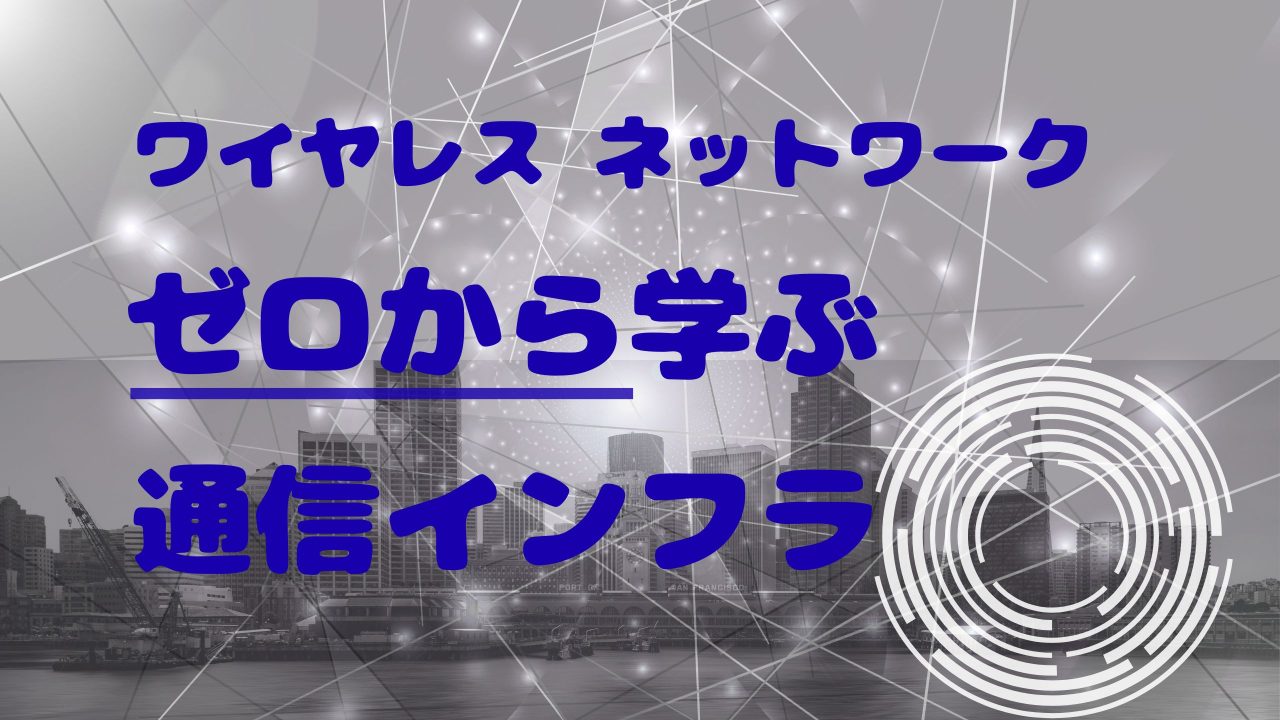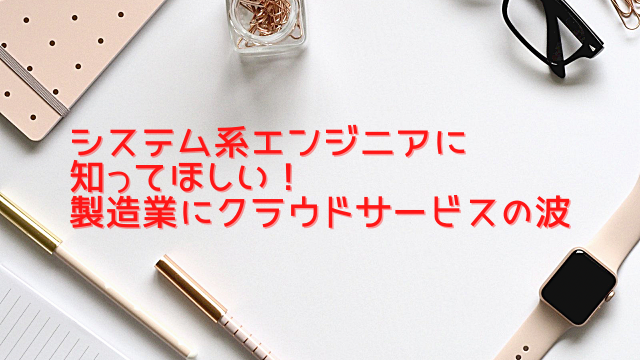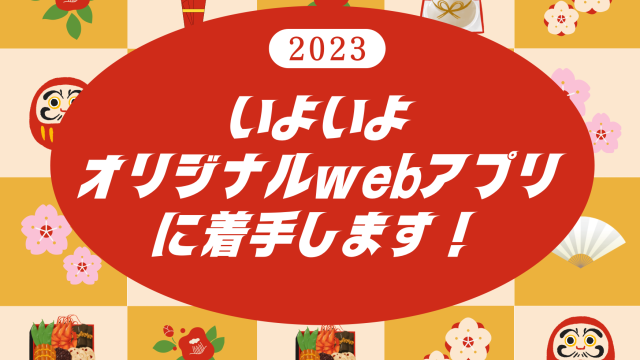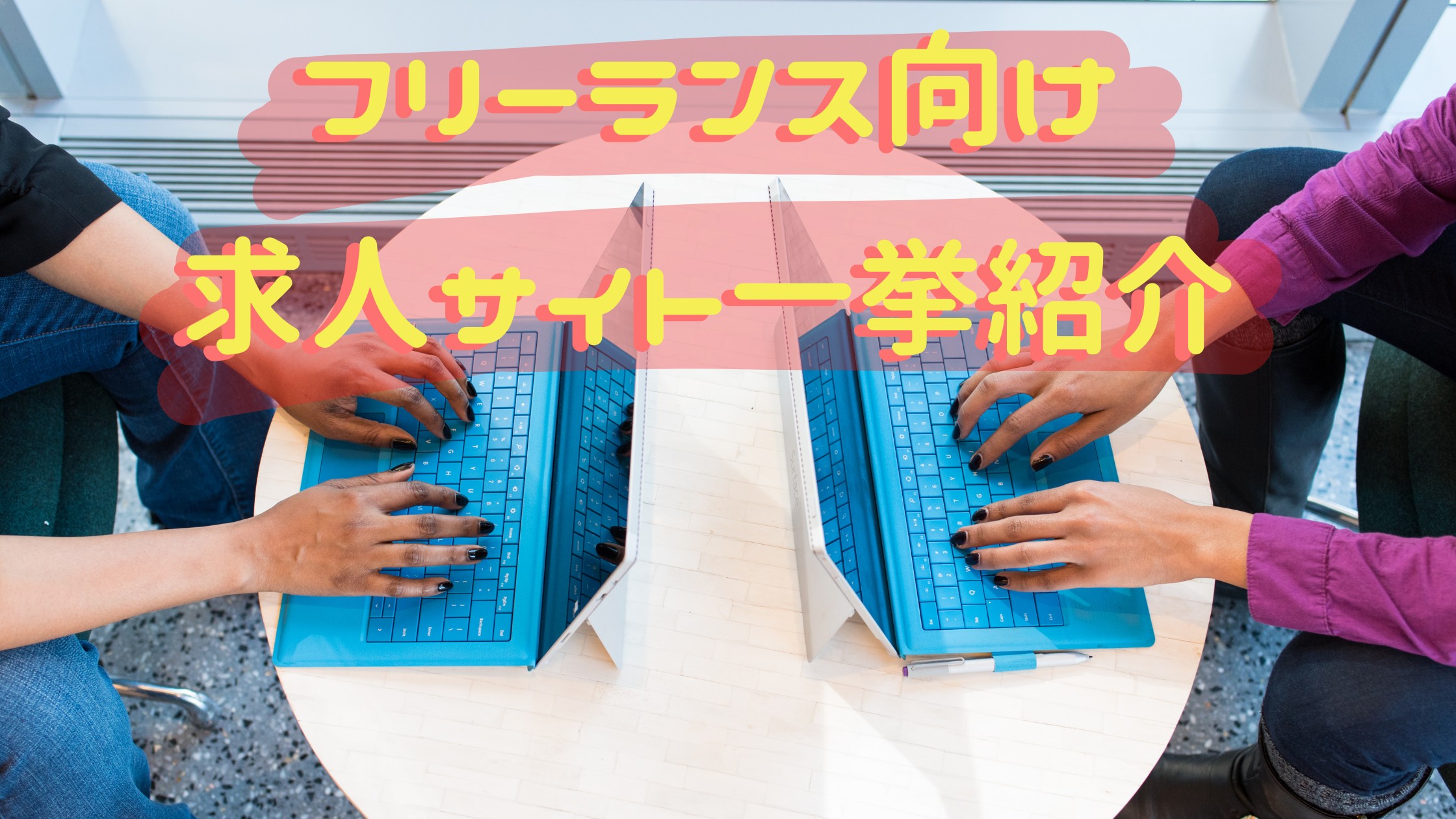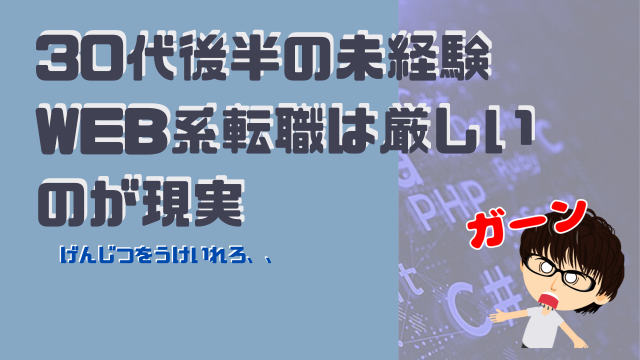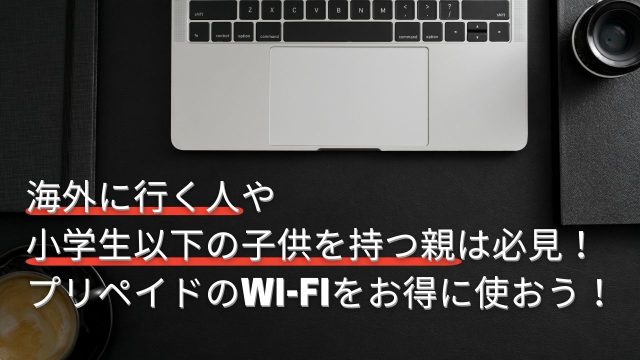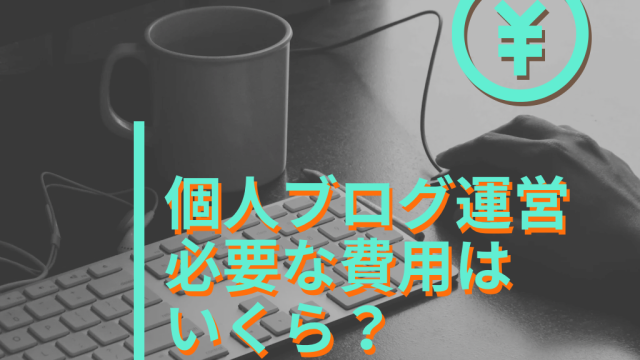【第2回】通信の“聞こえやすさ”を決めるSNRとは?
―電波が強いのに遅い理由を理解しよう
はじめに
5GやWi-Fiを使っていて、「アンテナは立っているのに通信が遅い…」という経験はありませんか?
それは、「電波の強さ(Power)」と通信の“質(Quality)”は別物だからです。
通信の“聞こえやすさ”を決めるのが、今回のテーマである SNR(Signal to Noise Ratio:信号対雑音比) です。
この記事では、SNRの意味・仕組み・目安をわかりやすく解説します。
1. SNRとは?
SNR(Signal-to-Noise Ratio)=信号の強さ ÷ ノイズの強さ
つまり、「信号がどれだけノイズに勝っているか」を示す数値です。
通信機器は、常に雑音(ノイズ)の中で信号を受け取っています。
ノイズが多ければ信号が埋もれ、正しくデータを解釈できません。
例:SNRの数値感覚
| 信号(mW) | ノイズ(mW) | SNR(比) | SNR[dB] | 状況 |
| 10 | 1 | 10 | 10dB | 通信可能(ややノイズあり) |
| 100 | 1 | 100 | 20dB | 安定通信 |
| 1000 | 1 | 1000 | 30dB | 非常に良好 |
| 1 | 1 | 1 | 0dB | 通信困難(ノイズに埋もれる) |
2. イメージで理解!音の世界にたとえると…
通信の世界では、音の聞き取りとよく似ています。
| 状況 | 音のたとえ | 通信での意味 |
| 静かな部屋で話す | 声がはっきり聞こえる | SNRが高い(ノイズ少ない) |
| 工事現場で話す | ノイズに声がかき消される | SNRが低い(通信困難) |
SNRは“信号の明瞭さ”を表す指標。
電波が強くてもノイズが多ければ通信は乱れます。
SNRが低いと「0」と「1」の違い(信号の変化)を読み取るのが難しくなります。
3. 電波強度(dBm)とSNRの違い
SNRとよく混同されるのが 受信電力(dBm) です。
| 指標 | 意味 | たとえ |
| dBm | 電波の“強さ” | 声の大きさ |
| SNR | ノイズとの“差” | 声の聞き取りやすさ |
例えば、工場内で大きな電波(−40dBm)が届いていても、
ノイズが多くてSNRが低ければ通信は遅くなります。
逆に、弱い電波(−70dBm)でもノイズが少なければ安定通信ができます。
4. SNRと通信速度の関係
SNRが高ければ、高度な変調方式(QAMなど)が使えます。
つまり、SNRが通信速度を決めるのです。
| 変調方式 | 必要SNRの目安 | 通信品質 | 備考 |
| BPSK | 約6〜8 dB | ノイズに強い | 低速通信向け |
| QPSK | 約10〜12 dB | 標準的 | 4G初期で使用 |
| 16QAM | 約18〜20 dB | 安定高速 | Wi-Fi等で一般的 |
| 64QAM | 約24〜26 dB | 高速 | LTE/5G標準 |
| 256QAM | 約30〜33 dB | 超高速 | 高品質通信環境 |
| 1024QAM | 約35〜38 dB | 最高速 | 5G/最新Wi-Fi6対応 |
SNRが足りないと、通信機器は自動的に低速モード(低次変調)に切り替えます。
通信速度はSNRで決まる。
電波が強くてもノイズが多ければSNRが下がり、
機器は自動的に低次変調に切り替えて「遅くても確実に届く」方式を選ぶ。
それが、「電波強いのに遅い」通信の正体です。
※SNRが低いと「安全な低次変調」に切り替える理由
通信機器(スマホ、Wi-Fiルーター、基地局)は、
リアルタイムで通信品質(SNR)を常に監視しています。
そして、もしノイズが多くてSNRが下がると、
「高次変調(1024QAMなど)」ではエラーが増えて再送信が必要になります。
再送が増えると、
結果的に通信速度が遅くなる+エネルギー消費が増えるので、
通信機器は自動的に「低次変調(QPSKや16QAM)」に落とします。
自動調整の仕組み(アダプティブ変調)
通信機器は常にこう動いています。
| SNRの状態 | 使用される変調方式 | 通信速度 | 備考 |
| 高い(30dB以上) | 1024QAM | 高速通信 | たくさんの情報を一度に送れる |
| 中程度(20dB前後) | 64QAM | 安定通信 | 標準的な速度 |
| 低い(10dB以下) | QPSK/BPSK | 低速通信 | エラーを防ぐために安全モード |
これを「アダプティブ変調と符号化(AMC: Adaptive Modulation and Coding)」と呼びます。
5. SNRとSINR・RSRP・RSRQの違い
通信分野では、似たような指標が登場します。
特に5Gでは「SINR」「RSRP」「RSRQ」がよく使われます。
| 指標 | 内容 | 使われる場面 |
| SNR | 信号対ノイズ比 | 通信品質の基本 |
| SINR | 信号対(干渉+ノイズ)比 | 5G/LTEでの実際の通信評価 |
| RSRP | 基地局からの信号強度(dBm) | 電波の強さを測る指標 |
| RSRQ | RSRPとRSSIの比率 | ネットワーク全体の混雑度を示す |
| RSSI | 受信信号強度 全体の電波の強さ(信号+ノイズ) | ざっくりした指標 ・−45dBm → 「基地局の目の前」レベルの強電波 ・−70dBm → 「部屋の隅でも使える」レベル ・−85dBm → 「壁や機械の陰でギリギリ通信」レベル |
ここでいう“全体”とは、信号+ノイズ+干渉すべてを含んだ強さのことです。RSSIはマイナスの値(dBm)で表され、0に近いほど強い信号を意味します。
SNRは純粋な品質、SINRは実際の環境品質。
SINRがSNRより低いのは、他の端末の干渉が加わるためです。
6.SNRが低下する原因(例:工場・プラント環境)
製造現場では、溶接機・インバータ・高電流モーターなどが強いノイズ源です。
これによりSNRが低下し、通信エラーや遅延が発生することがあります。
対策として:
- 通信機器を金属壁やノイズ源から離す
- 有線LANや光通信への切替
- 5GやWi-Fi 6のOFDMA/TWT機能を活用して干渉を分散
などが有効です。
7.SNRの目安と通信品質まとめ
| SNR[dB] | 状況 | 通信品質 | 備考 |
| 0〜5 | ノイズだらけ | 通信困難 | パケット損失多数 |
| 10〜15 | ぎりぎり通信可 | 不安定 | 遅延・再送が多い |
| 20〜25 | 安定通信 | 良好 | 一般的な品質 |
| 30〜35 | 高品質通信 | 快適 | 高速変調可能 |
| 40以上 | 非常に良好 | 極めて快適 | 1024QAM利用可 |
9. 一言でまとめると
SNRは“通信の明瞭さ”を表す数値。
電波の強さ(dBm)よりも、
「信号がノイズにどれだけ勝っているか」が通信の安定性を左右します。
次回の【第3回】では、
「5Gを支えるゲートウェイ・dBm・dBi」について詳しく解説します。
通信の“入り口”と“出口”であるゲートウェイが、
どうやって5Gと社内ネットワーク・クラウドをつないでいるのか。
また、dBm(電力) と dBi(アンテナ利得) の違いを、
図を交えてわかりやすく説明します。